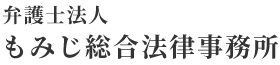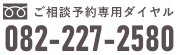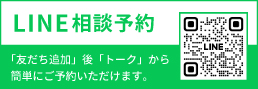-
●敷金とは何ですか?
敷金とは,不動産の賃貸借契約において,賃借人が賃貸人に対する賃料債務やその他の賃貸借契約に基づく債務を担保するために賃貸人に対して支払う金銭のことを言います。利息を付けずに,契約の終了時,賃貸人から賃借人に返還されるべきものとされています。
-
●敷金が返還される際,差し引かれるものはありますか?
敷金から差し引かれる金額は,賃料滞納分や原状回復に必要な費用などの借主が故意や重過失によって発生させた損傷や汚損,または契約書に明記された規定に違反した場合などです。しかし,通常の使用によって生ずる程度の損耗についての原状回復費用は敷金から差し引くことはできません。
-
●通常の損耗は敷金から差し引かれないとのことですが,例外はあるのですか?
賃貸契約書においても通常損耗に関する修理費用を賃借人が負担する場合には,その対象が具体的に明記されている必要があります。最高裁判所の判決によると,契約書に記載された明確な合意が必要であり,修理費用(金額)を明記した上で,それが通常損耗による場合でも賃借人が負担することが明記されている必要がある場合があります。ここで言う明記というものについては厳格なものが要求されており,また,賃借人が事業者,非事業者によってその程度が異なると言っていいでしょう。
-
●敷金の返還を請求できる時期はいつからですか?
敷金の返還を請求できる時期は,賃貸借契約の終了後,賃借人が不動産を明け渡した後からとなります。一般的には,賃貸借契約終了から1か月程度で敷金の返還が行われることが多いですが,契約書に別段の規定がある場合や,物件の状態に問題がある場合は,時間がかかることがあります。
-
●原状回復にかかわるガイドラインについて教えてください。
国土交通省が策定した「原状回復を巡るトラブルとガイドライン」は,建物の賃借人が居住や使用により発生した損耗や毀損を修復するための指針です。
ただし,このガイドラインにも,以下のような課題があります。
①ガイドラインでは,費用区分のすべてを明確に定められているわけではない。
②特別汚損かどうかは事実認定の問題になることも少なくなく,事案によってケースバイケースとなるため,ガイドラインだけでは解決できない。
したがって,原状回復に関するトラブルが発生した場合には,ガイドラインを参考にしながらも,事案ごとに状況を考慮した上で,解決策を模索する必要があるでしょう。 -
●賃料滞納により建物の退去・明渡を求める場合の流れについて教えてください。
① 内容証明郵便などの書面で未払い賃料の一括払いを求め,期限を区切ってその期限までに支払えない場合には,賃貸借契約を解除する旨の意思表示,及び期限までに滞納賃料が支払われない場合には,明渡を求めます。
② ①を前提にして,退去・明渡を交渉をするも,決裂した場合には,訴訟を起こします。
③ ②の裁判の中も和解での解決を探るも,それでも解決を図れない場合には,判決を得て強制執行をもって実現をすることになります。裁判の中でも和解での解決を図るのは,強制執行手続きを取る場合にも費用がかかることになるので,和解でのそれを図ることになります。 -
●普通建物賃貸借契約とはどのような賃貸借ですか。
期間を定め,又は期間を定めないで,建物の使用収益及びその賃料を定めてする, 法定更新のある建物賃貸借契約です。
建物の賃貸人が解約するには正当事由の存在が必要であり,賃借人が強力に保護された賃貸借です。1年未満の期間を定めた賃貸借契約は期間の定めのないものとみなされ,他方,1年以上であれば長期の制限はありません。 -
●普通建物賃貸借契約の法定更新はどのような場合に生じますか。
期間の定めがある賃貸借では,当事者が期間満了前1年前から6か月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知,又は条件を変更しなければ更新しない旨の通知をしなかったときは,従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます。また,当該通知後の場合でも,期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において,建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも,同様に契約を更新したものとみなされます。
次に,期間の定めのない賃貸借は,建物の賃貸人が解約の申入れをした日から6か月を経過することによって契約は終了しますが,この契約終了後においても,建物賃借人が建物の使用を継続し,これに賃貸人が遅滞なく異議を述べないときは,同様に契約は更新されたものとみなされます。 -
●普通建物賃貸借契約の法定更新後の契約期間についてはどのようになりますか。
期間は定めがないものとなります。よって,建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合において,解約の申入れの日から6か月を経過することにより,契約は終了しますが,解約の申入れの際には,正当事由の存在が必要です。
-
●普通建物賃貸借契約の解約における正当事由について教えてください。
①家主及び借家人 (転借人を含む) の双方の建物の使用を必要とする事情のほか, ②建物の賃貸借に関する従前の経過,③建物の利用状況, ④建物の現況, ⑤立退料の申出等を総合的に比較勘案して判断されることになります。
-
●建物賃貸借契約の解約の際の正当事由の各判断要素について教えてください。
①家主及び借家人(転借人を含む。)の双方の建物の使用を必要とする事情
正当事由の主たる判断要素なものです。
家主側の事情は,自己又は家族の居住の必要性,家族との同居の必要性,借家の老巧化による建替えの必要性,敷地の有効利用など,借家人側の事情は,借家の使用継続の必要性,(借家人(転借人)が老齢・病気・困窮等のため引越しが困難,借家人(転借人)生計を立てる手段として店舗に使用しているなど)が判断要素となります。
②建物賃貸借に関する従前の経過
契約締結の際の事情(恩恵的な貸借であったか(契約期間の長短,権利金・保証金・その他一時金の授受の有無及びその額など),契約の経過期間,借家契約継続中における更新料等の授受の有無・その額,賃料不払や用法違反等の債務不履行があるかなどが判断要素となります。
③建物の利用状況
建物が居住用か事業用か,その構造が堅固か,非堅固(木造)か,何階建か,床面積はどの程度か,建築基準法等に適合しているか,などの判断要素となります。
④建物の現況
建物の老巧化の程度(建物の経過年数や残存耐用年数),大修繕の必要性,修繕に必要な費用額などが判断要素となります。
⑤財産上の給付
①から④の正当事由を補完する要素であり,立退料の提供のほか,代替建物の提供が考えられます。 -
●通常の建物の賃貸借契約をすれば,容易に,退去,明け渡しをさせることができないとのことですが,一定の期間を経過すれば原則,退去,明け渡しをしてもらう契約の方法はありますか?
まず,一時使用目的の建物賃貸借契約を締結することが考えられます。
判例によると,「賃貸借の目的,動機,その他諸般の事情から,該賃貸借契約を短期間内に限り存続させる趣旨のものであることが,客観的に判断される場合」で,かつ,「賃借人もこれを了承しているような場合」に一時使用目的の賃貸借となるとされます。具体的には,建物を賃貸借する動機,建物の使用目的,用途,利用期間,建物の種類,敷金の有無等の賃貸借条件などの事情が考慮され,一時使用目的に該当するか判断されることになります。具体的には,自宅建物の増改築のための仮住まいなどがこれに該当するでしょう。なお,契約書に一時使用目的と記載されていても上記の要素を満たさなければ一時使用目的とはされません。
一時使用目的の建物賃貸借契約では,1年未満の賃貸借契約を無効としている借地借家法は適用されず(借地借家法第29条,第40条),民法がそのまま適用され,期間が満了後も,一時使用目的の建物賃貸借契約の賃借人が賃借物の使用又は収益を継続している場合,賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは,従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものとされ(民法第919条),契約の期間満了後は,期間の定めのない賃貸借となり,賃貸人及び賃借人ともに,どちらかからの解約申し入れから3か月後に賃貸借期間は終了する(同法第617条)。賃貸人からの解約申し入れについては,正当事由は不要とされます。
次に,定期借家権として,賃貸借契約を締結することです。
2000年3月1日施行以前の借家契約では,期間を定めていても,更新を拒絶するには正当な事由がない限り,賃貸人の方からの借家契約の更新の拒絶はできず,また,特約で更新しない旨を定めても,賃借人に不利な条項として無効になってしまいます。これに対して,定期借家契約では,契約で定めた期間満了によって,契約を終了させることができることになります。
但し,定期借家契約には以下の要件を満たすことが必要とされています(借地借家法38条)。
① 書面により契約をすること
② 契約期間を定めること
③ 契約書の中に,契約の更新がなされないということを定めておくこと
④ 契約の前に,契約の更新がないことにつき書面をもって説明しておくこと
特に,③については,「契約の更新がなく,期間が満了すれば契約は終了する」というような定めをすることが一般的でしょう。
④については,契約の締結前に,契約の更新がなく,期間の満了により契約が終了する旨を書いた書面を借主に渡し,説明することを必要とし,この書面は契約書とは別に作成しなりません。なお,この説明の時期は,契約締結の前であればよく,契約締結と同じ日でも差し支えありません。
成立の際には上記の通りなのですが,定期借家契約を終了させるためには,期間満了の1年前から6か月前までの間に,期間満了により契約が終了する旨の通知をしておく必要があり(但し,その契約の期間が1年未満の場合は不要)。この通知を行っておけば,期間満了時に契約は終了し,借主に出て行ってもらうことができます。
もっとも,契約の終了後に,新たに定期借家契約を結び直すということは可能です。 -
●賃貸建物について,立ち退きを求められています。立退料の相場はいくらなのでしょうか?
そもそも,立退料そのものだけで,立退きの肯否が決せられるものでなく,立退きの際に判断される正当事由の存否の判断について,補完するものという位置づけです(借地借家法第28条)。
定型的な算定方法はなく,諸々の要素と関連して定まるとされ,その理由の一として,現実の紛争においては,当事者間の話合い, 民事調停,訴訟になった場合でも和解で解決することが多く,閲覧可能な記録としては残らないことがあるのではないでしょうか。
居住用,事業用共通して,移転実費および借家権価格相当額, 事業用の場合はさらに営業補償を加味して算定するものとされ,不動産鑑定評価基準にも算定方法が存在しますが,裁判例では必ずしもこれに従って立退料の金額が決められていません。賃貸人および賃借人が建物の使用を必要性や,賃貸借に関する従前の経過 老朽化に伴う建替えの必要性等を総合的に考慮して判断されます。
としても,一般的に,居住用の場合よりも事業用のほうが高額になる傾向があり,居住用の場合,賃借人の被る不利益, 移転費用 賃貸人の使用の必要性等の事情を考慮し,事業用の場合には,物件の立地条件,賃借人の被る不利益,固定客の状況やこれまでの営業の月日数などの事情が考慮されるでしょう。
あくまで,私見でありますが,概ね,家賃の6ヶ月~1年分 ,居住用の場合には,40万~80万円,事業用の場合には,300万~1億円などの相場観ではないでしょうか。 -
●建物賃貸借契約の解約の際の正当事由の存否の判断基準時について教えてください。
判例は,解約申入れの時から6か月間持続することを要し,かつそれで足り,その後の事情は正当事由判断の資料とはならないとし,借家人が賃貸借契約の解約申入れに基づく建物明渡請求訴訟を継続維持しているときは,解約申入れの意思表示が黙示的・継続的にされているものと解すべきであるとしています。当該解約申入れ当時に正当事由が存在しなくても,訴訟係属中に正当事由が具備するに至った時から6か月の期間の経過により,当該賃貸借契約は終了するとしています。
他方,賃貸人が解約申入後に立退料等の金員の提供を申し出た場合又は解約申入時に申し出ていた右金員の増額を申し出た場合においても,右の提供又は増額に係る金員を参酌して当初の解約申入れの正当事由を判断で,右正当の事由を補完する立退料等金員の提供ないしその増額の申出は,事実審の口頭弁論終結時までにされたものについては,これを考慮することができるとしています。
借家における正当事由は,原則,解約申入れの時から6か月間持続することを要し,かつそれで足るとしつつ,立退料等の提供の申出のみが事実審の口頭弁論終結時までできるものとしていると捉えられるでしょう。 -
●家賃債務保証会社について教えてください。
賃借人から委託を受け保証料の支払を受けて,連帯保証人になることを主たる業務の内容としている業者のことを言います。
一般に,賃借人は家賃債務保証会社に保証料として賃料の半月分を支払い,2年目ごとに当該保証料を支払うとされることが多く,家賃を滞納した場合,賃借人に代わって賃貸人に家賃を支払い,家賃保証会社が賃借人に求償することになります。 -
●建物を賃借しています。賃料1回の未払いで契約解除されてしまうのでしょうか。
賃料未払いを含め,債務不履行による賃貸借契約の解除については,単に債務不履行があったのみならず,それにより賃貸借契約を継続し難い事情があるときに解除権の行使が認められます。
なお,建物賃貸借契約において賃料1か月の遅滞で無催告解除ができる旨を定めた特約条項については,契約を解除するに当たり催告をしなくてもあながち不合理とは認められないような事情が存する場合には,無催告で解除権を行使することが許される旨を定めた約定であると考えるべきであり,原則として単に1か月の不払で無催告解除ができるという特約は無効です。 -
●家賃債務保証会社について教えてください。
賃借人から委託を受け保証料の支払を受けて,連帯保証人になることを主たる業務の内容としている業者のことを言います。
一般に,賃借人は家賃債務保証会社に保証料として賃料の半月分を支払い,2年目ごとに当該保証料を支払うとされることが多く,家賃を滞納した場合,賃借人に代わって賃貸人に家賃を支払い,家賃保証会社が賃借人に求償することになります。 -
●つい最近,賃借人が自殺をしていた場合,賃貸人は,新たな賃借人に対して自殺の事実を告知すべき義務がありますか。
はい。
入居者の自殺は,心理的に嫌悪感を生じる事由(心理的瑕疵)であるということができ,賃借するか否かを決める重要な要素となります。ですから,賃貸人は,少なくとも自殺後間もない時期に新たに賃貸する場合には,この事実を告知しなければなりません。
これを怠ると,告知義務違反を理由として,詐欺により賃貸借契約を取り消すことができ,また,賃借人は損害賠償も請求できる余地があります。 -
●建物賃貸借契約でペットの飼育を一律に禁止する条項は有効ですか。これに違反した場合,契約解除されますか。
一般的には,一律にでも犬や猫などのペットの飼育を禁止する条項の有効性を認めています。なお,裁判例としては,この条項違反のみを根拠に賃貸借契約の解除を認めるものがあるほか,他の要素(例えば,室内や廊下等が汚れたなどの事情等)を考慮し,賃貸人と賃借人との間の信頼関係が失われたことを理由に解除を認めるものもあります。
-
●私が契約した建物賃貸借契約書に「大音響でテレビ,ステレオ等の操作,ピアノ等の演奏を行うことを禁止する」旨の条項があります。この度,騒音のクレームを受けましたがどの程度の騒音で契約解除になりますか?
生活する上で,生活音を発することはやむを得ないことですが,生活上我慢すべき限度(受忍限度)を超えている場合には,上記の条項違反となります。受忍限度を超えているかは,騒音の大きさ,種類,時間帯,頻度,やむを得ないものか等が判断基準となります。また,この基準に該当する騒音であって,中止することを何度も催告されてもそれに従わないときは,賃貸借契約の解除が有効となる可能性が高まります。
-
●ペット可の物件で小型犬を飼っていました。この度部屋を解約したのですが,壁やフローリングの汚損にかかわる費用を請求されました。契約書には,これらの費用は借家人が負担するという特約があります。しかし私はゲージの中で小型犬を飼っていたので,壁や床等を傷つけたことはなく経年変化によるものです。支払わなければならないでしょうか?
小型犬による壁,床等の破損ではないのですね。そうすると,そもそも,質問の中での特約の有効性については,借家人において通常損耗以上の修繕等の義務を負担する認識があったか否かが問題となりますが,一般には否定的です。そうすると,本件の賃借人は請求されるものを負担する必要はないと考えられます。
-
●賃貸で店舗を経営しており,賃料は,売上げに応じてスライドすることになっています。最近ビルのオーナーから,周囲の店舗建物の賃料が増加傾向にあることを理由に,賃料の増額を求められました。賃料が営業売上げに応じて変わるのに,さらに増額されることがあるのでしょうか。
売上げに応じて賃料がスライドする建物賃貸借契約であっても,建物の賃料が,租税維持管理費火災保険料などの負担の増,土地・建物の価格の上下,その他の経済事情の変動により,または相場の変動により近隣の同種の建物の賃料に比べて著しく不相当となったとき,賃料の増額が認められる可能性があると言えるでしょう。
なお,事例判断ですが,最高裁は,このような特約は借地借家法32条1項ただし書で規定する賃料不増額の特約に該当するものでもないとし,賃料増額請求権を認めました。 -
●私は賃貸家屋の大家です。更新時期が間もなく来ますが,賃借人に家賃の値上げを求めたところ,拒否されました。この時,法的にどのような手段をとることができますか。
地代又は家賃の賃料の値上げ・値下げについては,当事者間での話し合いによって決めるのが原則です。この協議が調わないときは,原則として簡易裁判所に民事調停の申立てをすることが必要(調停前置主義)です。そして,調停が不調に終わったときは,賃料の増額請求訴訟を提起することになります。
なお,裁判が確定するまでの間の賃料について,賃借人は,増額を正当とする裁判が確定するまでは,自ら相当と考える賃料の額(従前の賃料額が相当と考えれば従前の賃料額であるが,それより低額であってはならない。)を支払えばよいとされています。 -
●事業用定期借地権とはどういうものですか。
事業用定期借地権とは専ら事業の用に供する建物(居住用を除く。)の所有を目的とする借地権のことで,いずれも公正証書によって借地契約を締結する必要があるものです。スーパーマーケット,医院,家電量販店等に多く,必ず公正証書によって締結されなければなりません。存続期間を30年以上50年未満である借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権と存続期間を10年以上30年未満である借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権があるものとされます。
-
●退去時のトラブルを避けるため,入居時に注意することはありますか?
入居時に賃貸人・賃借人が立ち会って部屋の状態を確認し,チェックリストや写真で記録しておくことが大切です。損傷の発生時期が明確になり,退去時の修繕費用をめぐるトラブルを防ぐことができます。
-
●建物を借りる際気を付けることはありますか?
契約は当事者の合意で自由に決められるため,契約内容を十分に理解し,特に原状回復などについて賃貸借契約書をよく確認することが大切です。
-
●賃貸借契約(契約更新を含む)では,借主に不利な特約でもすべて有効なのでしょうか?
借主に不利な特約でも,借主がその内容を理解し,同意していれば有効とされる場合がありますが,基本的に借地借家法や消費者契約法に反する内容は無効とされることが少なくないと思われます。
特に原状回復に関する不利な特約については,合理的な理由があり,借主が内容を理解し,同意していることが必要です。 -
●家賃の支払義務はいつから発生しますか?
家賃の支払義務は,基本的に契約期間の開始日から発生します。ただし,物件が入居可能な状態にない場合は,実際に入居可能となる日から支払いを開始するのが適切です。
-
●気に入った物件があったので契約しましたが,契約日の翌日を契約の始まりとされました。私の事情で,まだ引っ越しの準備ができておらず1か月程度後でないと入居ができません。家賃を支払わなければならないですか?
入居していなくても,物件が入居可能な状態で契約が開始していれば,基本的に家賃の支払義務は生じます。
ただし,自分の事情で入居が遅れる場合でも,契約始期を遅らせられないか貸主と相談する余地はあります。
-
●賃貸物件の修繕について,借主が修繕する義務はありますか?
借主は原則として修繕義務を負わず,貸主の責任です。
なお,「借主が修繕する」との特約がある場合でも,原則は貸主の義務を免除するだけで,借主に修繕義務を課すものではないと考えられています。
-
●賃貸物件の蛍光灯が切れましたが,自分で替えたほうがいいですか?
原則として借主は修繕義務を負いませんので,貸主に通知する義務があります。ただし蛍光灯のような小規模な修繕は,借主が自己負担で交換することもできます。
-
●子供の大学進学のため、賃貸住宅を借りようと申込書に記入し、「申込金」として、1万円を支払いました。しかし、その後、地元の大学に合格したため、キャンセルしたいのでが,可能ですか?
キャンセルできます。なお,賃貸契約前に支払った申込金は「預かり金」とみなされ,契約が成立していなければ返還を請求できます。
-
●借りている物件のお風呂の給湯器が壊れ,修理会社に連絡したところ,給湯器を新しくする必要があると言われました。大家さんにこの費用を負担してもらえるのでしょうか?
原則として,取り替えを要求することができます。
-
●シャワーのホースが破損し,大家さんに修繕をお願いしているのですが,いまだに直してもらえません。自分で勝手に直してもいいですか?
原則として,貸主の承諾が必要です。
-
●アパートの結露によって壁紙にカビが生え,クレームを入れたのですが,大家からは,住み方が悪いのだから自分でなんとかするように言われました。私は自分で壁紙を貼り替えないといけないのでしょうか?
貸主に通知もせず,拭き取るなどの手入れを怠った場合,賠償すべきとされる余地あるでしょう。これらの借主としてすべき義務を履行している場合には,借主に修繕の義務はないとされています。
-
●洗面所で水漏れがあったので調べてもらったところ,配水管の老朽化による水漏れだといわれました。大家からは,使い方が悪いのだから自分で修繕するように言われました。私は自分で修繕しなければいけないのでしょうか?
通常の生活の範囲内の使用方法であれば,借主は修繕義務を負わないと考えられます。配水管は居住に必要な設備ですので,貸主が修繕義務を負います。
-
●共用の廊下の蛍光灯が消えたままで危ないと思うのですが,どうすればいいでしょうか?
対応は管理委託契約の内容によります。貸主に相談が原則となるでしょう。
-
●水漏れなどの,物件の設備の修繕費用を大家に請求できますか?
借主は,貸主に対し,修繕について事前に通知する必要があります。そのうえで,必要な修繕については,原則として貸主が修繕義務を負います。
-
●突然水漏れしたので,大家に連絡する前に急いで修理してもらいました。修繕費用を大家に請求できますか?
緊急に修理する必要があった場合は,応急程度もしくは普通の修繕であれば,その費用を請求できると考えられます。
-
●母の遺産整理中,母の土地上に誰も住んでいない建物がありました。建物の所有者が既に亡くなっているようです。どうすればいいですか?
建物収去土地明渡請求は,建物所有者に対して行います。 建物の登記名義人が亡くなっている場合,その相続人が建物の所有者となります。戸籍を調べて相続人を特定し,相続人全員に対して建物収去と土地明渡しを求める必要があるでしょう。
-
●借家人が行方不明となり,家賃も払われていない状況です。部屋の中の物は処分して,次の人に貸してもよいでしょうか?
借家人の荷物を勝手に処分すると,民事上や刑事上の責任を問われる可能性があります。まずは賃貸借契約を正式に解除し,建物の明渡しや未払賃料の支払いを求めて訴訟を起こし,判決に基づいて強制執行を行う必要があります。
-
●退去時,畳の表替費を請求されましたが,支払う必要はありますか?
原則として支払う必要はありません。畳の裏返しや表替えは,次の入居者のためのアップグレードとされ,通常の使用による変色やへこみは借主の責任になりません。
ただし,飲み物のシミや雨による変色など,借主の不注意による損傷は,原状回復義務が生じる可能性があります。
-
●壁紙に染み付いたタバコの臭いについて,原状回復費用を支払う必要はありますか?
支払う必要がある場合が多いです。国土交通省のガイドラインでは,タバコの臭いは通常の使用を超える損耗とされ,借主に原状回復義務が生じる可能性があります。
なお,喫煙が禁止されていた場合は,契約違反とみなされ,損害賠償責任が発生する可能性もあります。
-
●壁に釘を打って棚を設置してできた穴について,原状回復費用を支払う必要はありますか?
穴の程度によっては支払う必要があります。国土交通省のガイドラインでは,下地ボードの貼り替えが必要なほどの損傷は「通常使用の範囲を超える」とされ,原状回復費の負担が求められる場合があります。
-
●隣室の迷惑行為にはどう対応すればいいですか?
まずは貸主に事情を説明し,注意などの対応を求めるのが適切です。貸主には,建物を居住に適した状態に保つ義務があり,迷惑行為がそれを妨げる場合は,加害側の借主に対して改善を求める責任があります。
-
●迷惑行為がひどい場合の対応はありますか?
賃貸物の損傷や近隣への影響が大きく,信頼関係が破壊されたと認められる場合,貸主は契約解除も可能です。ただし,軽微な場合は,過去の注意履歴や周辺への影響なども考慮されます。
被害を受けた借主は,加害者に損害賠償請求ができる場合もあります。
-
●地震でガラスにひびが入ってしまいました。修理費を負担する必要がありますか?
原則として,負担する必要はないと考えられます。国土交通省のガイドラインでは,自然災害による損傷については借主に責任がないとされており,修理費の負担は求められないケースが多いです。
-
●ペットがドアをひっかいて傷がついてしまいました。原状回復費用を支払う必要がありますか?
負担する必要がある可能性が高いです。国土交通省のガイドラインでは,ペットによる傷は通常の使用による損耗とは認められないため,借主の負担と判断されるケースが多いとされています。
-
●退去時の損傷の確認サインをしましたが,届いた原状回復費用の請求が思っていた以上に高額でした。一度サインをしてしまった以上,支払わなければならないのでしょうか?
サインした内容が損傷の確認だけであれば,費用負担に同意したことにはなりません。ガイドラインや契約書の特約に基づいて,本来賃借人が負担すべきかどうかを判断することになります。
また,費用負担に同意していた場合でも,故意・過失によらない損傷であれば,原則として賃借人が負担する必要はありません。 -
●原状回復を,賃借人である私が指定した業者にしてもらうことはできませんか?
通常,賃貸人が原状回復工事を行い,その費用を敷金などで精算する「金銭賠償方式」が一般的です。ただし,「賃借人が原状回復を行う」と契約書に記載のある場合は,自分で選んだ業者に依頼することも可能と考えられます(としても,賃貸人への相談はするべきです。)。その際,元の状態と同等の材質・仕上がりで修繕しないと,やり直しを求められることがあります。
-
●賃借人の善管注意義務とは何ですか?
賃借人の「社会通念上求められる程度の注意を払って賃借物を使用する義務」のことです。特に建物の賃借では,日常的な清掃や退去時の清掃など,適切な管理が求められます。
-
●賃借人の善管注意義務を怠るとどうなりますか?
不注意により通常以上の損耗・損傷を与えた場合,善管注意義務違反となり,損害賠償の対象になることがあります。例えば,掃除を怠ったことによるカビ,飲み物の放置や結露によるシミなどが挙げられます。
また,設備の故障などで修繕が必要な場合は,賃貸人に速やかに通知する義務があり,通知を怠ると被害拡大による賠償責任を問われる可能性があります。
-
●物件を明け渡した後、賃貸人から原状回復費用の明細が届きません。明細を請求できますか?
請求できます。賃貸人には,敷金から差し引く原状回復費用の具体的な内容を説明する義務があり,賃借人は,その明細の提出や説明を求めることが可能です。
-
●退去時に部屋全体のクリーニング代を請求されましたが,支払う必要はありますか?
賃借人が通常の清掃(ゴミの撤去・掃除・水回りの汚れ取りなど)をしていれば,次の入居者のためのクリーニングとなるため,原則として貸主負担とされています。
ただし,日常的な手入れ不足によるものと判断された場合は,賃借人の負担となることもあります。
-
●退去時に鍵の取り替え費を請求されましたが,支払う必要はありますか?
原則として,支払う必要はありません。入居者が退去した後の鍵の交換は,物件管理上の理由(防犯など)で行われるものであり,賃貸人の負担とするのが妥当とされています。
-
●不注意で壁のクロスの一部に張替えが必要なほどの傷をつけてしまいました。部屋全部のクロス張替費用を負担しなければならないですか?
賃借人は,不注意で生じた傷について修理費用を負担する必要がありますが,部屋全体ではなく,原則,損傷箇所を含む「一面分」までの張替えが妥当とされています。
-
●賃貸物件を退去する際,賃借人から事前告知は必要ですか?
必要です。なお,事前告知の要否や期間は,契約の種類や内容によって異なります。
-
●退去の事前告知は,どのように行えばよいですか?
当事者間の合意に基づいて,書面や口頭など,契約で定められた方法に従ってください。