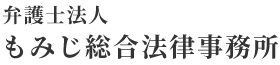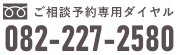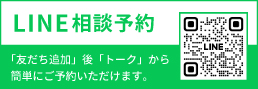個人再生とは
-
●個人再生とは何ですか?
個人の債務を整理するための手続きとしては,破産,個人再生,任意整理,特定調停の各手続があります。その内,個人再生とは,借金を減額して,その減額した額を原則3年間で分割して支払うことが出来れば,残りの借金は免除される手続きをいいます。
個人再生手続きには,「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」とがあります。
-
●個人再生の特徴・メリットとはどのようなものですか?
個人再生と破産は,裁判所が関与する手続きという点で共通ですが,以下の点で大きな違いがあります。
・誤解を恐れず言ってしまえば,破産は借金が0となりますが,個人再生は借金の一部を支払わなければなりません。
・破産は原則財産を全て処分されますが,個人再生は財産を処分する必要はありません。
・破産の場合,一定の期間,生命保険外交員や警備員などの職業に就けなくなりますが(資格制限),個人再生の場合はそのような制限はありません。
このような違いから,個人再生は,破産の場合の資格制限に該当する職業に就いている方や,処分されたくない財産を保有されている方にメリットのある手続と言えます。特に,住宅ローン付の住宅を手放したくない場合にはきわめて有効な手続です。
-
●小規模個人再生と給与所得者等個人再生の違いについて教えてください。
①要件との関係で,小規模個人再生はできるが給与所得者等個人再生はできない場合があること,②給与所得者等個人再生の場合は最低弁済額が小規模個人再生の場合よりも多額になる可能性があること,③小規模個人再生の場合は,債権者の反対によって返済計画である再生計画案が否決される可能性があること,などが大きな違いです。
手続について
-
●どこの裁判所に申立てをすればいいのですか?
生活の本拠である住所地を管轄する地方裁判所に申立てをします。単身赴任等の理由により住民票上の住所と生活の本拠地が異なっている場合,生活の本拠地で申立てをすることができます。
-
●申立ての実費にはどのようなものがありますか?
申立手数料,予納郵券,官報公告費用として2~3万円が必要となります。また,事務処理に必要な郵便代・各種書類取寄費用等が必要となります。
-
●手続の大まかな流れを教えてください。
①申立て→②手続開始決定→③債権者の債権届出→④申立人の異議申述→⑤再生計画案提出→⑥書面による決議又は意見聴取→⑦再生計画の認可決定→⑧官報公告掲載の流れで進みます。官報に掲載された日の翌日から2週間経過後,認可決定が確定します。
-
●最終的に手続きが終わるまでどれくらいの時間がかかりますか?
受任をしてから,認可決定が確定するまで,7~8か月かかります。なお,事案によって期間は伸長します。
-
●個人再生では,いくら払えば残りの債務が免除されますか?(最低弁済額)
小規模個人再生では以下の①②,給与所得者等再生では以下の①②③によりそれぞれ算出される金額の最も多い金額を支払わなければなりません。
①負債総額からの算出する金額
住宅ローンを除く債務の総額が
100万円未満 総額全部
100万円以上500万円以下 100万円
500万円を超え1500万円以下 総額の1/5
1500万円を超え3000万円以下 300万円
3000万円を超え5000万円以下 総額の1/10
②財産(清算価値)から算出する金額
破産をしたら換価される財産の価額
③収入(法定可処分所得額)から算出する金額
収入から所得税・住民税・社会保険料を控除し,さらに政令で定められた生活費を差し引いた金額の2年分
よって,収入の多い方については③の基準により支払額が多くなる場合もあり,その場合は小規模個人再生を申し立てることが考えられます。 -
●個人再生手続の再生計画ではその弁済期間は原則3年とされると聞きましたが,それ以上の期間の返済計画で認められる余地はないのですか?
3年を超えることの特別の事情が認められれば5年を超えない範囲において許される場合があります。実際の実務においてもしばしば5年の範囲において認められています。
-
●友人に対する債務のみ弁済をしたのですが,個人再生を利用することができますか?
特定の債権者に対する債務弁済行為や財産を廉価で売却する行為など,破産手続における否認対象行為でありますが,破産手続ではありませんから,否認権の行使によって否認対象行為が取り消されることはありません。
しかし,「不当な目的で再生手続開始の申立てがされたとき」「申立てが誠実にされたものでないとき」といった当該偏波弁済行為が悪質と評価され,それに伴い個人再生の申立てとされる場合には,申立てが棄却されることがあります。
なお,棄却されなかった場合でも,当該否認対象行為によって減少した額を民事再生手続きの中で上乗せして弁済する必要があるでしょう。 -
●個人再生手続き中に「積立て」が必要と聞きますが,「積立て」とはどのようなものですか。
個人再生認可決定確定後,再生計画に従って返済が開始しますが,その返済の予定額を積み立てるもので,通常,代理人口座に入金・振込をして積み立てるものです。将来,再生計画に基づいて返済ができるかどうか(履行可能性)の判断材料となります。
-
●積み立てた金額は,清算価値に計上されますか?
裁判所によって運用が異なりますが,広島地方裁判所では,再生手続開始決定前の積立金は,破産事件であれば自由財産の範囲拡張の対象になると見込まれるものを除き,清算価値に計上されます。再生手続開始決定後の積立金については,清算価値に計上しない扱いになっています。
-
●給与が,借入れをしている銀行口座に振り込まれています。このままにしていても大丈夫ですか?
借入れをしている銀行に弁護士から受任通知を送付すると,預金口座が凍結され出金することができなくなるのが一般です。出金することができなくなると,日々の生活費の支払に困ることになりますので,現金払いにしてもらうか,振込口座を変更してもらうのがよいでしょう。
-
●少額の債権者に対しては,個人再生認可決定確定後,一括で支払うことができますか?
1回の支払額が振込手数料を下回るような少額の債権者に対しては,再生計画案に少額債権の定めをすることによって,一括払いをすることができます。
-
●住宅ローンを滞納したため,住宅ローン債権者により競売を申し立てられました。個人再生の申立てをすることで,競売を止めることができますか?
個人再生手続の申立てをしただけでは,競売手続を止めることはできません。個人再生手続の申立てとともに,抵当権実行手続中止の申立てをして,抵当権実行の中止命令を得ることにより競売を止めることができます。
要件について
-
●元金の他,利息を含めると5000万円以上の借金とその他,3000万円ほどの住宅ローンを抱えています。この場合に個人再生手続きを利用することができますか?
まずは利息について引き直し計算を確認する必要があるでしょう。それで5000万円を超えない場合には利用することができますが,それでも5000万円を超える場合には,個人再生を利用することはできません。この場合,通常の民事再生手続の利用が考えられますが,個人再生と比較して,予納金が高額であること,手続が複雑であること,要件が厳格であることなどの理由から利用は困難です。
-
●個人再生を利用するための要件にはどのようなものがありますか?
小規模個人再生の要件としては
①将来において継続的又は反復的な収入の見込みがあること
②住宅ローンを除いた総債務額が5000万円を超えないこと
給与所得者等再生の要件としては,
上記①②に加え
③給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり,かつ,その変動の幅が小さいと見込まれること
④過去に破産手続等の免責許可決定を受けている場合,免責決定が確定してから7年を経過していること
⑤過去に給与所得者等再生手続が認可された場合,認可決定が確定してから7年を経過していること
が必要となります。 -
●自分の収入だけでは,個人再生に基づく弁済を履行することが困難ですが,配偶者の収入を併せて考えれば,履行することが可能です。この場合も個人再生を利用することができますか?
同居で家計が同一の親族については,その収入を含めた家計全体から履行可能性を判断されるので,個人再生を利用することができます。
他方,家計が別の親族の収入については,その収入が継続的なものであり,収入の一定額を再生債務者の家計に組み入れることが継続的に可能であれば,利用できる可能性もあります。
申立人について
-
●私はまもなく定年なのですが,個人再生を利用することができますか?
間もなく定年になるとしても,年金受給,再雇用,再就職などで,「将来において継続的又は反復的な収入の見込みがある」といえれば,個人再生を利用することができます。
-
●私は現在失業中ですが,個人再生を利用することができますか?
失業中であっても,間もなく就職することが決まっていて「将来において継続的又は反復的な収入の見込みがある」といえれば,個人再生を利用できる可能性があります。
-
●個人事業主ですが,個人再生を利用することができる場合がありますか?
個人事業主も「将来において継続的又は反復的な収入の見込みがある」といえれば小規模個人再生を利用することができます。また,「給与」は給与所得者の給与に限られませんので,定期的な収入を得る見込みがあり,かつ,その変動の幅が小さいと見込まれれば,給与所得者等再生も利用することができます。
-
●年金受給者や所得がアルバイト収入である場合も個人再生を利用することができますか?
年金が老齢年金や退職共済年金の場合には,継続的な収入を得る見込みがあるといえるので,利用することができます。アルバイトの場合も,雇用実績が短期間ではなく,雇用が相当期間継続している実績がある場合には利用することができます。
-
●専業主婦・主夫でも個人再生を利用することができますか?
将来において無収入の場合は,「継続的に又は反復して収入を得る見込み」が無いので利用することはできません。しかし,就職の内定を得ている場合など,将来において「継続的に又は反復して収入を得る見込み」があると言える場合には,利用することができる可能性があります。
-
●勤務先や親友からの借入など,一部の債権者を除外して個人再生を利用することができますか?
除外することはできません。除外したことで再生計画が不認可とされる危険があります。
-
●借金の原因がギャンブルですが,個人再生を利用することができますか?
破産では免責不許可事由「浪費・賭博・その他の射幸行為」に該当しますが,個人再生の再生計画不認可の理由に当然にはなりません。利用することが可能です。
-
●個人再生手続中に債務者が死亡しました。手続はどうなりますか。
①申立後,再生計画認可決定確定前に債務者が死亡した場合は,再生手続は終了し,申立てたこと自体が法的には無という扱いになります。相続人としては,相続債務を免れるためには,相続放棄ないし限定承認を検討する必要があります。②再生計画認可決定確定後に債務者が死亡した場合は,債務者の相続人は,再生計画認可決定の確定により変更された再生債務を相続します。この場合も,相続債務を免れるためには,相続放棄ないし限定承認を検討する必要があります。
債務について
-
●税金を滞納していますが,税金も個人再生によって減額することができますか?
税金など公租公課は一般優先債権とされ,再生手続によらないで随時弁済しなければならず,減額することもできません。
-
●離婚後,養育費を払っていますが,個人再生の手続きの中で,養育費はどのように扱われますか?
再生手続開始決定前に発生した未払の養育費は,再生計画によって権利の内容を変更することができません。よって,減額することはできません。
また,再生手続開始決定後に発生する養育費は,共益債権として随時弁済することができ,債権者一覧表に掲げる必要もありません。 -
●契約をしている生命保険から契約者貸付を受けています。この貸付は,個人再生の手続きの中でどのように扱われますか?
契約者貸付は,解約返戻金の前払いと考えられていますので,債権者一覧表に記載する必要はありません。
解約返戻金見込額から借入額を控除した残額が清算価値の対象となる財産となります。 -
●個人再生の場合には債権者から反対されることで手続きが頓挫しませんか?
小規模個人再生では,返済計画である再生計画が裁判所によって認可されるためには,債権者数の半数以上の反対がなく,かつ,反対をした債権者の債権額総数が2分の1を超えないことが必要となります。よって,同手続きでは債権者の反対により頓挫することがありえます。しかし,給与所得者等再生では,このような要件は必要ではありません。
よって,個人再生手続に反対をする債権者が多いと予想される場合や,2分の1以上の債権を有する債権者が反対をすると予想される場合は,給与所得者等再生を申し立てることを検討することになります。 -
●給与が差し押さえられていますが,これを止めることができますか?
①申立後,再生手続開始決定前,②再生手続開始決定後,再生計画認可決定確定前,③再生計画認可決定確定後の各段階に応じて取りうる手段・効果が異なります。
① 申立後,再生手続開始決定前
差押をしている再生債権者に「不当な損害」を及ぼすおそれが無い場合に限り,裁判所に対して執行手続を中止するよう申立てをすることができます。
② 再生手続開始決定後,再生計画認可決定確定前
申立て後,再生手続開始決定がなされた場合,再生手続開始決定正本を添付した強制執行手続中止の上申書を執行裁判所に提出すると,給与差押など強制執行等の手続は中止します。
③ 再生計画認可決定確定後
再生計画認可の決定が確定した場合,認可決定正本・認可決定確定証明書を添付した強制執行失効の上申書を執行裁判所に提出すると,強制執行等は失効します。 -
●借金の中に,保証人が付いている債務があります。個人再生の手続きは,保証人にどのような影響を及ぼしますか?
再生計画は,債権者が保証人に対して有している権利に影響を及ぼさないのが原則です。よって,主債務者に支払停止などがあれば,債権者は保証人に対して請求をするのが通常です。
-
●個人再生手続開始決定後,再生計画案提出前に,家族の治療費の支払いのため生命保険から契約者貸付を受けて支払ってもよいでしょうか。
家族の治療費の支出は,通常は詐害性が認められず支払っても問題にはならないと考えられます。治療費として支払った金額についても清算価値に加える必要はないと考えられます。
財産について
-
●個人再生の手続きの中で,退職金はどのように扱われますか?
再生計画認可時に退職していない場合は,仮に退職したらいくらになるかという退職金見込額の8分の1が清算価値算定の対象となります。
他方,再生計画認可時に既に退職金を受領していた場合は,現金ないし預貯金の形になっているので,現金・預貯金など(破産事件であれば自由財産の範囲拡張の対象となる財産)と併せて99万円を超えるものは全て清算価値の対象となります(広島地方裁判所の場合)。 -
●確定給付企業年金や確定拠出年金に加入しています。これら年金は清算価値算定の対象になりますか?
確定給付企業年金,確定拠出年金は,いずれの場合も差押禁止財産であり,清算価値算定の対象にはなりません。
-
●所有権留保付きの自動車は,個人再生の手続きの中でどのように扱われますか?
留保所有権を有する債権者から,車の返還請求をされることが通常です。
その債権者が,自動車の場合は登録,軽自動車の場合は引渡しを受けていれば,対抗要件を具備しているものとして,返還請求を拒絶することは困難です。 -
●再生手続中に親が死亡しました。遺産を取得しないで手続きを進めることができますか?
通常,被相続人が亡くなってから3か月以内であれば,相続放棄により遺産を取得することなく,手続を進めることができます。
他方,自らの取得分をゼロとする遺産分割協議の場合には,その協議が否認対象行為とされ,その協議によって減少した額を清算価値に加えなければならない可能性があります。 -
●個人再生の手続中に,父が死亡しました。父の遺言書によると,私の遺留分が侵害されています。個人再生手続との関係で遺留分侵害額請求はどのようになりますか?
遺留分侵害額請求権は行使上の一身専属権であり,行使するかどうかは自由です。行使すれば清算価値に算入されますが,行使しない場合は清算価値に算入されません。
-
●子どもの学資保険など,現在契約をしている生命保険の契約を継続することはできますか。
継続することができますが,解約返戻金見込額が清算価値の対象となる財産となります。
-
●借家に住んでいて敷金を差し入れています。個人再生手続ではどのように扱われますか?
敷金返還請求権も財産なので財産目録に記載しなければなりませんが,自宅の敷金については,清算価値の対象とならないのが一般です。
-
●個人再生手続開始決定後,再生計画案提出前に,家族の治療費を支払ったため,積立金を積み立てることが難しくなりました。積立金を積み立てるため保険金を解約してもよいでしょうか?
積立金の積立が難しくなった原因が家族の治療費の支払というのであれば,実質的に,保険の解約返戻金をその支払いに充てたといえ,解約したこと自体は許されると考えられます。但し,保険を解約しなければ積立ができないという事情が,将来の弁済の履行可能性の判断に影響するものと考えられます。
-
住宅資金特別条項について
-
●住宅資金特別条項を利用しての個人再生により残すことのできる「住宅」とはどのようなものですか?
本人が所有し,本人が居住していることが必要です。
よって,専ら事業の用に供している場合や専ら他人の居住の用に供している場合は,個人再生手続きの住宅ローン特例によって残すことは困難です。 -
●二世帯住宅として利用をしている場合には住宅資金特別条項を利用できますか?
可能です。ただし,当該建物の床面積の2分の1以上を専ら自己の居住用に利用していることが必要です。
-
●住宅が配偶者と共有名義になっている場合も,個人再生によって住宅を残すことができますか?
共有名義の場合でも住宅資金特別条項を利用することができ,住宅を残すことができます。
-
●住宅資金特別条項を利用しての個人再生申立てをする前に当該住宅に対して差押えがされている場合には住宅資金特別条項を利用が可能ですか?また,それが税の滞納によるものである場合にはどうですか?
前段の単なる差押えの場合には利用が可能です。最終的に再生計画の認可決定がでることで,差押えの手続きの効力がなくなるからです。他方,後段の税の滞納である場合には利用できないと考えるべきでしょう。税の滞納の場合には原則,そのまま換価手続きに進んでいくことで再生債務者が住宅の所有権等を失う可能性が高いからです。
-
●住宅に当該住宅ローン以外の債務を担保するために後順位の抵当権が設定されている場合には住宅資金特別条項を利用が可能ですか?
条文上,できません。
-
●住宅ローン以外の債務について延滞をし,住宅ローンについても延滞をしてしまっている場合,住宅資金特別条項によって当該住宅ローンを弁済することができますか?
期限の利益を喪失したと言えない場合には弁済することができますが,期限の利益を喪失したとされる場合には原則として弁済することができません。しかし,後者の場合にも債権者と交渉することで期限の利益が再度付与される場合には可能ですので迅速な対応が望まれるところです。
-
●住宅ローンの債務について,保証会社による代位弁済がなされている場合,住宅資金特別条項付個人再生を利用することができますか?
代位弁済から6か月を経過する日までに再生手続開始の申立てをする必要があります。
その後,住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が確定した場合,保証債務の履行はなかったものとみなされるので,住宅ローンの支払いは元々の債権者に対してすることになります。 -
●住宅ローンの債務のほか,その住宅(マンション)の管理費を滞納しています。このような場合に住宅資金特別条項を利用することができますか?
マンションの管理費は先取特権であり,別除権付再生債権として扱われます。別除権が存在したままでは,住宅資金特別条項を利用することができないので,管理費の滞納を解消する必要があります。この場合,偏頗弁済行為とならないよう親族等の援助による弁済が望ましいです。
-
●住宅資金特別条項付きの個人再生申立てを行い,開始決定が出ました。その後,再生計画案提出前に,住宅ローンの連帯債務者となっていた父が死亡し,住宅ローンが団体信用生命保険により完済しました。個人再生手続上,どのようになりますか?
住宅ローンの抵当権等が設定されている不動産については,通常,不動産の時価額から抵当権等の被担保債権残額を控除した金額が清算価値となります。しかし,再生計画認可決定前に住宅ローンが完済されると,不動産の時価額が清算価値として計上することになります。結果,清算価値が増大し,最低弁済額も非常に高額になるため,弁済計画の見通しが立たなくなります。この場合は,裁判所にその旨を上申して廃止決定をしてもらい,個人再生以外の方法も検討することになるでしょう。
-