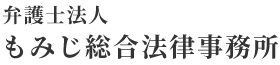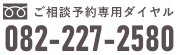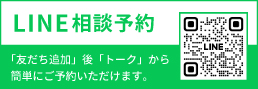破産の申立て
-
●破産申立とは何ですか?
債務超過などによって債務の返済が困難になった会社または個人の財産を裁判所が換価し,これを全債権者に平等に配当して清算し,個人の場合には,債務者の生活の再建を図ることを目的とする手続です。破産の申立は,債権者も取ることができます。債権者が破産手続開始の申立てをすることを債権者破産申立と呼びます。
-
●自己破産の手続の流れを教えてください。
弁護士に相談→受任の通知≒本人への取り立ての中止→裁判所に提出する書類の準備→裁判所に自己破産の申立て→自己破産手続の開始→免責の許可が大まかな流れです。
-
●どこの裁判所に申立てることになりますか?
債務者が営業者の場合は主たる営業所の所在地等を管轄する地方裁判所に申立てをします。
債務者が営業者でない場合は,第1に債務者の住所,第2に居所,第3に住所・居所がないとき又は知れないときは最後の住所地を管轄する地方裁判所に申立てをします。 -
●破産できない確率はどのくらいですか?
2020年の日本弁護士連合会の調査によれば,免責が許可された割合は98%程度,申立てを取り下げた割合が1%程度であり,免責不許可となった割合は1%を割っています。
-
●勤務先に知られないようにできますか?
破産手続開始決定や免責許可決定が出ると官報に掲載されますが,一般の人が官報をチェックしていることは稀ですから,勤務先に知られる可能性は少ないでしょう。
但し,裁判所へ提出する書類には,勤務先から入手しなければならないものがあることに注意が必要です。 -
●司法書士に依頼する場合と,弁護士に依頼する場合とで何が違うのですか?
司法書士は申立書類の作成をすることができますが代理権を有しないので,手続きの期日での立ち合いをすることができません。他方,弁護士はそのような制限はありません。
-
●個人破産の弁護士費用の相場はいくらですか?
約30万~約60万程度で事件の内容によって増減します。
-
●弁護士費用を消費者金融などから借りてもいいですか?
借金の返済ができないという事情から破産を申し立てるという状況の中,弁護士費用を消費者金融などから借りれば,詐欺罪にもなりえますので,絶対にしてはいけません。
-
●弁護士費用を準備することが困難です。どうすればいいですか?
法テラスの定める資力などの要件を満たせば,法テラスが弁護士費用を立て替えてくれます。ただし,管財事件の場合の予納金については,原則,法テラスは立て替えてくれないので,自分で,予納金の準備をする必要があります(ただし,生活保護を受給している場合は除く。)。
-
●法人破産の場合についても,法テラスに立て替えてもらうことができますか?
法人の破産については利用することができません。
-
●破産予納金とは何ですか?
破産予納金とは,破産手続において裁判所に支払う費用です。
-
●破産予納金を法テラスに立て替えてもらうことができますか?
自分で用意する必要があります(生活保護受給者の場合には20万円を限度として,法テラスの立て替え払いの対象となる可能性あり。)。
-
●弁護報酬以外にどのような費用がかかりますか。
同時廃止事件となると申立手数料,予納郵券,官報公告費用で一般的には1万数千円程度でその多くは済みます。他方,管財事件となると,申立手数料,予納郵券,官報公告費用の他,管財人に支払われる引継予納金,これは数十万円と高額なものとなることもありますが,簡易なものであれば低額で済むこともあります。
-
●破産した場合のデメリットを教えてください。
・官報に掲載される。
・破産手続中,警備員や宅建士など一定の職業につくことができない。
・ブラックリストに登録されローンを組むことが非常に難しくなる。
などがあります。
しかし,
・戸籍に掲載される
・選挙権を喪失する
・携帯電話などが解除される
などは都市伝説であり,そのようなデメリットはありません。
-
●破産した場合,どのような職業に就くことができませんか?
破産手続開始決定から免責許可決定が確定するまでの間,一例として,以下の職業に就くことが制限されます(記載されているものが全てではありません)。
弁護士,司法書士,税理士,公認会計士,社会保険労務士,不動産鑑定士,公証人,警備業者,警備員,生命保険募集人,損害保険代理店,宅地建物取引業者,宅地建物取引士,建設業,貸金業者,後見人,後見監督人,保佐人,保佐監督人,補助人,補助監督人,遺言執行者 など -
●破産申立てをすると取締役を続けることができなくなりますか?
破産手続開始決定を受けると,法律上,当然に取締役の地位を失います。しかし,再度,取締役に選任されることは妨げられません。
-
●破産手続中,住所を変更することができますか?
申立前は,住所変更に制約はありません。
申立後,手続が管財事件となった場合には,裁判所の許可が必要になります。 -
●住民票上の住所と実際の居住地が異なる場合,どちらの裁判所に申立てをしますか?
実際の居住地を管轄する地方裁判所に申立てをすることになります。
-
●借入先をぜんぶ覚えていません。破産できますか?
基本的にはできます。預金履歴の出金履歴を確認したり,信用情報を照会することによって覚えていない借入先を調査することになります。
-
●借金がいくらなら破産できるのですか?
「借金がいくら以上なら自己破産をすることができる」という基準はありません。債務の総額と収入・財産を比較して判断をすることになります。
-
●どのような場合,自己破産できますか?
現在の収入・財産によって,将来借金を返済することが著しく困難である状況,つまり,「支払不能」であることが条件とされています。
-
●「ブラックリスト」とは何ですか?
信用情報機関に延滞や債務整理などの情報が載ることを「ブラックリスト」と言われています。
-
●同時廃止で法人代表者個人の破産手続が進められますか。
管財事件として処理されます。法人関係の財産調査の必要性を考慮し,必要がないといった例外的な場合に限り,同時廃止手続で処理される可能性があります。
-
●弁護士に依頼をすると,債権者からの連絡や請求が止まりますか?
弁護士が債権者に対して受任通知を行うと,通常,債権者からの連絡や請求は止まります。
-
●自己破産の申立の準備には,どれくらいの期間がかかりますか?
債権調査にかかる時間,必要書類を集める時間,さらに申立書類を作成する時間がありますので,個人差が大きいです。
-
●具体的に,破産の申立は何を準備するのでしょうか?
借金の総額,借入先の数,初めて借金を始めた時期とその事情,返せなくなった時期とその事情等を申立書に記載します。また,今の家計収支の状況を家計簿として何か月か記録します。その根拠となる資料(収入の資料等)についても準備します。
-
●自己破産の申立ての前に過払金を請求できますか?
過払金請求はできます。その場合,その旨を裁判所へ申告しなければなりません。
-
●破産手続中に借り入れをしてもいいですか?
してはいけません。
このようなことをすると,破産手続での免責不許可となる可能性が高いです。 -
●任意整理しましたが,返済が苦しいです。自己破産できますか?
任意整理の返済中でも,自己破産の手続は可能です。
-
●借金について法律相談をする際,持っていくものはありますか?
借金の総額,借入先の資料,ご自身の財産の状況がわかる資料があるとスムーズに相談が進みます。
-
●自己破産は何回でもできますか?
自己破産に回数制限はありません。ただし,前回の破産と破産の理由が同じであるなど,認められづらくなる可能性はあります。
-
●借入先が一社しかありませんが,破産できますか?
借入先が一社であっても破産できます。
-
●破産手続の準備中に,時効にかかっている借金があった場合,どうなりますか?
時効援用できるものについては,時効援用の手続をします。
-
●未払いの医療費は自己破産できますか?
未払の医療費は自己破産によって免責されます。
-
●夫婦それぞれの名義で借金があり,一緒の家計で借金を返済しています。夫,または妻のみ破産することはできますか?
原則としてできます。
-
●夫(妻)名義の借金があり,私には収入が十分ありますが,返す必要がありますか?
原則,保証人になっていない限り払う必要はありません。しかし,借金の原因が日常家事債務である場合,返済する必要がある場合もあります。
-
●日常家事債務とはなんですか?
夫婦の日常的な生活を送るためにできた借金のことで,食費,日用品,医療費,光熱費,子供の教育費,家賃などがこれに該当します。
-
●自動車を手放したくないので,一時的に名義を他の人に変えていいですか?
財産隠しとみなされるため絶対にやめましょう。
-
●投資によってできた借金は破産できますか?
原則として,投資による借金は浪費行為として免責不許可事由に該当し,免責できない可能性もあります。
-
●ペットは財産として扱われますか?破産によって手放さなければならなくなる可能性はありますか?
破産手続上は,ペットも破産者の財産として扱われます。また,ペットが回収されてしまうことはほとんどないと考えられますが,破産の原因がペット費用であったり,ペットローンが残っている中での破産では,飼い続けることができない可能性もあります。
開始決定
-
●すべて財産が取り上げられますか?
一定の財産については,手元に残すことが認められています。これを「自由財産」といいます。
-
●自由財産にはどのようなものがありますか?
本来的自由財産とそれ以外の自由財産があります。前者には99万円以下の現金,生活に欠くことができない衣服や寝具、家具などがあります。後者には,通勤や日常の生活を送るのに欠かせない場合で、自動車などがあげられます。
-
●自動車を持ち続けることができますか?
ローン残の所有権留保付の自動車の場合,対抗要件(自動車は登録,軽自動車は引渡)を具備している債権者から返還を求められると,それを拒めません。ローン完済した自動車の場合で,高価値の車は破産財団として換価処分,他方,評価額の低い車は換価処分されず,持ち続ける可能性があります。
-
●破産手続で処理できなかった債務はどうなりますか?
個人の場合は免責手続で債務の支払義務を免除されることがあります。他方,法人に対してはこの種の手続きは存在しません。
-
●法人破産にも,自由財産というものがありますか?
ありません。
-
●電話利用料を支払ってスマートフォンを使用できますか。
通話料,通信料などについて現金で支払うことは問題ありません。但し,クレジットカードで決済する支払方法では支払えません。
-
●スマートフォン端末代金を分割で支払っています。分割支払いを続けてもいいでしょうか?
原則,できません。ただし,例えば,親族などに援助してもらい残債を一括で支払ってもらうことは問題ありません。
-
●自己破産の手続きは,どのくらいの期間がかかりますか?
同時廃止事件になる場合と管財事件になる場合とによって異なります。
管財事件であれば,一般的には申立から約6ヶ月~1年くらいです。
同時廃止事件であれば,一般的には申立から約3ヶ月~6ヶ月くらいです。 -
●「管財事件」とは何ですか。
破産手続開始の決定と同時に選任された破産管財人が,財産の調査や換価,債権調査,免責調査,その他清算処理を行う事件をいいます。
-
●「同時廃止事件」とは何ですか。
管財事件とは異なり,破産手続開始と同時に破産手続は廃止になる事件をいいます。さらに個人の場合,最終的に免責を認めるかどうかを裁判所が判断するための免責審尋後,裁判所によって免責許可(不許可)の決定が出ます。
-
●管財事件と同時廃止事件は,どのようにして振り分けられますか?
一定以上の財産がある場合,免責不許可事由の程度が軽微でない場合,法人代表者や個人事業主の場合には管財事件となります。
-
●管財事件になった場合,破産管財人と面談することはありますか?
はい,あります。破産管財人との面談で,調査のため,破産の申立書類の内容を確認されます。通常,面接は30分~1時間ほどで終了します。
-
●免責されない債務とはどのようなものがありますか?
税金や国民健康保険料などの租税,罰金など刑事事件にかかわる債務など,免責されない債務も存在します。これらを「非免責債務」といいます。
-
●債務を故意に乗せなかった場合,どのような制裁を受けますか。
個人の場合には免責が認められなくなることがあります。
-
●どのようなことで免責が不許可になりますか?
財産を隠匿する,財産を無償(または不当に安い金額)で譲渡する,クレジットで購入した物品を不当に安い金額で換金する,一部の債権者にだけ返済をする(偏頗弁済),浪費やギャンブルによって借金を増やした,過去7年の間に免責許可を受けた,などの事由があると,免責が不許可になってしまうとされています。
ただし,免責不許可事由がある場合でも,事情によっては,裁判所の裁量によって免責が許可されることもあります。 -
●給与が差し押さえられています。止めることができますか?
【同時廃止事件の場合】
破産手続開始決定正本及びこれを停止文書とする旨の上申書を執行裁判所に提出することで,破産者の財産との関係で執行手続は中止されますが,給与の4分の3の範囲で受け取れることになります。免責許可決定が確定した場合は,免責許可決定正本及び確定証明書並びにこれを取消文書とする旨の上申書を執行裁判所に提出することで,給与の全額を受け取れます。
【管財事件の場合】
原則,破産手続開始決定が発令された時点で,破産手続開始決定「正本」及びこれを取消文書とする旨の上申書を執行裁判所に提出することで,破産財団との関係で執行処分は取り消され,この時点で,将来の給与の全額を受け取ることができます。 -
●退職金はどのようになりますか?
手続開始決定の時点で,退職したら支給されるであろう見込額の8分の1が破産財団に組み入られますが,自由財産拡張によって,預貯金,保険解約返戻金などとあわせて99万円の範囲内であれば,自由財産として認められるのが通常です。
-
●住宅ローンが付されたマンションはどうなりますか?
ほとんどにマンションについて抵当権が設定されているので,抵当権が実行をされ所有権を失うことが多いでしょう。ただし,個人再生手続で回避する可能性はあります。
-
●賃貸のアパート契約は解除されますか?
基本的に,自己破産をすること自体で契約が解除されることはありません。
-
●免責の判断基準は何ですか?
破産法252条1項各号に定められている免責不許可事由にあたらないかを判断します。
-
●破産手続開始決定後に債権者一覧表にすべての債権者を記載しない場合,どのようなペナルティがありますか。
個人破産の場合,一部の債権者が記載されていない債権者一覧表を提出したことが,免責不許可事由となる危険があります。また,破産者が知りながら債権者一覧表に記載しなかった債権者の有する請求権は,非免責債権となり引き続き請求をされる危険があります。
-
●破産手続開始決定後に新たな債権者が判明しました。どのようにすればいいですか?
直ちに,債権者を追加する旨,裁判所に上申し,債権一覧表に追加しましょう。
-
●免責許可決定はいつ確定しますか?
免責許可決定の事実が官報に掲載されてから2週間が経過したときに免責許可決定が確定します。免責許可決定が出てから官報に掲載されるまで約2週間かかりますので,免責許可決定が出てから約1か月後に確定することになります。
-
●給与が債権者である銀行口座に振込まれています。このままでいいですか?
一般的に,銀行に弁護士からの受任通知が届くと口座が凍結されます。振込先を債務を負担していない銀行の口座に変更することが望ましいでしょう。
-
●現在の仕事に影響は出ますか?
基本的に,影響はありません。同じ会社で働く,あるいは新しい仕事を始めるということもできます。
もし知られたとしても、自己破産を理由に解雇されることもありません。ただし、前述したとおり一部の職業は就くことができないことがあります。 -
●債権者集会とは何をするのですか?
債権者に対して,破産手続の進捗状況や財産状況などを債権者に報告し,意見を聴取します。
-
●債権者集会を病気や入院で欠席できますか?
病気や入院の場合には,正当な理由として欠席が許されると考えられます。
-
●債権者集会を無断欠席したらペナルティはありますか?
裁量免責すべきかどうかの判断をしますが,その判断の中で不利益な印象を与えるため,無断欠席は望ましくありません。
-
●子供のために学資保険を積み立てているのですが,破産すると解約しなければなりませんか?
解約返戻金が一定額を超える場合は解約となり債権者への返済に充てられることになります。
-
●保証人がいる借金があるのですが,私が破産すると保証人も支払わなくてよくなりますか?
本人の債務が免責されても,保証人の保証債務は免責されません。保証債務を支払うことができなければ,保証人自身も債務整理を検討することになります。
-
●家族の財産はどのようになりますか?換価されてしまうのでしょうか?
家族が所有している財産は処分されません。但し,家族の財産を取得する費用が破産をする人の財産から支払われている場合には,債権者への返済に充てられる可能性があります。
-
●生命保険は解約しなければなりませんか?
県民共済など解約返戻金がない保険は,契約を継続することができますが,解約返戻金がある保険については,解約返戻金が一定額を超える場合は解約となり,原則,債権者への返済に充てられることになります。
-
●破産すると,年金を受給できなくなりますか?
自己破産をしたとしても,年金受給資格に影響はありません。
-
●破産すると,選挙権はなくなりますか?
自己破産をしても選挙権が制限されることはありません。被選挙権も制限されません。
-
●破産すると,住民票や戸籍にその情報が記載されますか?
記載されません。
-
●生活保護を受給中です。破産すると,生活保護はもらえなくなりますか?
生活保護に影響はなく,支給は継続します。
-
●クレジットカードで購入した商品はどうなりますか?
その商品の所有権がクレジット会社に留保されている場合には,クレジット会社に引き揚げられる可能性があります。
-
●家賃を滞納しています。破産の手続中に支払ってもよいのでしょうか?
滞納家賃の支払は,偏頗弁済となり,免責不許可事由に該当します。その結果,免責が得られないことになる可能性があります。
-
●個人的に返済したい債務を除いて破産することは可能ですか?
してはいけません。すべての債務を裁判所へ申立て,破産手続をする必要があります。
-
●債権者に訴訟を提起されています。破産申立できますか?
はい。債権者から訴訟を提起されている,強制執行をされているといった場合でも,破産申立をすることは可能です。
また,破産手続開始決定時に係属する強制執行についてはその効力を停止失効することになりますが,破産管財人の判断により続行されることもあります。なお,抵当権など別除権などに基づくものなどはその効力に影響がありません。 -
●自ら原告となって裁判係属中です。破産が開始された場合にどうなりますか?
人格権や身分上の権利に関する訴訟など,破産財団に関しない訴訟については,破産者自身が訴訟を追行します。
他方,金銭債権の請求訴訟など破産財団に関する訴訟については,破産手続開始決定により中断します。その後,管財人が訴訟を受継するか,あるいは,破産手続開始前に相当程度訴訟が進行していた場合には,従前の訴訟代理人が訴訟を引続き追行することもあります。 -
●最近,離婚に伴い不動産を財産分与として渡しました。問題はありますか?
不相当に過大であり,財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情のない限り,詐害行為とはなりませんが,右特段の事情がある場合には,不相当に過大な部分について,その限度において詐害行為として取り消される可能性があります。
-
●離婚のときに取決めをした養育費,慰謝料を滞納しています。破産をすることによって,免れることができますか?
養育費は,滞納分も将来発生分も,支払義務を免れることはできません。
慰謝料については,「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」「故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」でなければ免責され,支払義務を免れることができます。 -
●破産手続中であった親が死亡しました。息子の私は,どう対処すればいいですか?
申立後,開始決定前に死亡したとき,相続債権者や相続人等の申立てにより,裁判所は破産手続続行の決定をすることができますが,続行されなければ,破産手続は終了します。
他方,破産手続開始決定の決定後に死亡したときは,当然に破産手続が続行されます。
このように,死亡した後も破産手続が続行することが多いですが,免責手続は続行することなく終了します。よって,相続人としては,相続放棄の申述をする必要があります。 -
●勤務先から借入れがあり,給料から天引で支払っています。このままでよいでしょうか?
勤務先からの借入れも銀行や消費者金融からの借入と同じであり,天引きは偏波弁済にあたるので,勤務先に天引きを止めるよう問い合わせをする必要があります。
-
●申立後,住所を変更した場合,申立てとの管轄に影響しますか?
申立後に住所の変更があっても管轄に影響はありません。
-
●借金の原因がギャンブルです。破産できますか?
免責不許可事由となりますが,ギャンブルの程度や反省,今後の生活の立て直しの見込みなどにより,裁量で免責を得る余地があります。
-
●以前,一度破産をしています。再び破産をすることができますか?
できます。ただし,前回の免責許可決定が確定した日から7年を経過しなければ,免責が認められません。
-
●奨学金を返済中です。破産するとどうなりますか?
免責が得られれば,奨学金残債を支払う必要はありません。ただし,親などが連帯保証人になっていれば,その方が支払わなければなりません。
-
●滞納している税金はどうなりますか?
税金は免責されません。しかし,手続のなかで届け出る必要はあります。
-
●自己破産をすると,債務の保証人はどうなりますか?
本人が自己破産をして免責を受けたとしても,保証人の保証債務は免除されませんので,保証債務を支払うことができなければ,保証人も債務整理を検討することになります。
-
●自己破産をすると,新しく賃貸アパートを借りることができなくなりますか?
基本的には借りることができますが,保証会社を保証人として利用を指定される契約の場合,その物件は借りることが難しくなる場合があります。
-
●予納金を支払わない場合,破産申立はどうなりますか?
一定期間内に所定の予納金を支払わない時は,申立てが却下されます。
-
●滞納している家賃はどうなりますか?
破産開始決定前に滞納している家賃は免責されます。
-
●自己破産手続中に結婚式や葬式に出て,祝儀や香典を出してもいいですか?
冠婚葬祭費用は一般的に認められる傾向にあり,一般的に考えられる金額であれば問題ないと考えられます。交際費として家計収支表に記載した上で,裁判所に提出します。
-
●通勤に自動車がないと困るのですが,自己破産手続で自動車を引き揚げられた後,新しい車を購入できますか?
ローンを組むことはできませんので,一括購入で,かつ,自動車の価値が低額であれば認められる可能性があります。
-
●破産手続中,ネットショッピングはできますか?
自己破産の場合,クレジットカードは解約されるので全て使えなくなります。ただし,デビットカードを使ってネットショッピングをすることはできます。
-
●破産手続中,スマホ決済は使えますか?
前問と同様に,デビットカードを使ってスマホ決済をすることはできます。
-
●自己破産手続中に新しい口座を開設してもいいですか?
借入先の金融機関でなければ問題ありません。
免責
-
●免責とは借金がなくなるということですか?
正確に言えば,借金を支払わなくてもよくなるということであって,借金が消えてなくなるわけではありません。そのため,保証人がついている場合は保証人が支払わなければならなくなります。
-
●免責によってすべての債務が免責されますか?
すべての債務が免責されるということにはなりません。
-
●免責審尋とは何をするのですか?
免責をするかどうか裁判官が判断をするために,裁判官が申立人と面談をして様々な質問をします。
-
●免責審尋を病気や入院で欠席できますか?
病気や入院の場合には,正当な理由として欠席が許されると考えられます。
-
●免責審尋を無断欠席したらペナルティはありますか?
裁量免責すべきかどうかの判断をしますが,その判断の中で不利益な印象を与えるため,無断欠席は望ましくありません。
-
●破産後に借金返済の書面が来たのですが,なぜですか?
①免責許可が出たことを把握していない
②税金や損害賠償の支払などの支払義務が免除されない債権である
③自己破産申立時に債権者としてあげていなかった
④闇金など
が主な理由として考えられます。
いずれにしても,一度弁護士に相談されることが望ましいでしょう。 -
●自己破産手続後に新しいスマートフォンを購入してもいいですか?
分割払いは破産後しばらく(5年から10年)利用できませんが,現金の一括払いであれば問題ありません。